過去の歴史を振り返ると、日本株よりも米国株のほうが株価の上昇率が大きいため、FIREを目指す場合は米国株を中心に投資すべきだと一般的に言われています。
現在は比較的円安の状況が続いており、米国株を中心に資産を形成してきた方は、円ベースでの資産評価額が高くなっており、円安の恩恵を感じているかもしれません。
一方で、将来の為替情勢は誰にも予測できず、過去の2010年前後のように、1ドル=100円以下の円高相場に戻る可能性もあります。
なので、今回の記事では、将来為替がどちらに振れても、慌てずにいられるよう、円安・円高それぞれのメリットとデメリットをできるだけ分かりやすく解説し、それぞれに対する対策や具体的な行動計画を紹介します。
円安・円高とは
円安・円高とは、一般的に米ドルに対して日本円の価値が安いか高いかを比較した言葉です。
もう少し分かりやすく言うと、円安は【米ドルよりも円のほうが弱い状況】、つまり1ドルを買うために、より多くの円を払わなければなりません。
反対に、円高は【米ドルよりも円のほうが強い状況】で、1ドルをより少ない円で買うことができます。
「1ドル〇〇〇円を超えたら円安」といった絶対的な基準は存在しません。
そのため、ニュースやインターネットなどで【今は円安】というような記事を見かけたら、
「今は以前と比べて【比較的】円が安いんだな」くらいに思っておけばよいと思います。
円安のメリット・デメリット
なんとなく「円安は円がドルよりも弱いこと」というのは分かったけれど、
それが実際に自分の生活や資産にどう影響するの?ということを知りたい方もいらっしゃると思います。
そこで、円安のメリットとデメリットを簡単に紹介します。
円安のメリット
- 米国株など海外の金融商品の円建ての評価額が上がる
もしあなたがS&P500のインデックスファンドなど、米国株の金融商品をすでに保有している場合、円安下では円がドルよりも弱いため、円に換算するとより多くの金額になります。
例えば、100ドル分の米国株を保有していたとして、1ドル=100円のときは10,000円の価値ですが、1ドル=200円に円安が進むと、20,000円と日本円で価値が倍になります。 - 日本の輸出企業が儲かる
外国に物やサービスを販売する日本企業は、基本的にドルなどの外貨を海外の顧客から受け取っています。
その売上を円に換算すると、より多くの金額になります。
そのため輸出企業に勤めている方は給料が増える可能性があり、日本の輸出企業の株を保有している場合は、株価が上がったり配当金が増えたりする可能性があります。
円安のデメリット
- 米国株など海外の金融商品の円建ての価格が割高になる
FIREを目指したり将来の資産を増やす目的で、S&P500のインデックスファンドなど米国株の金融商品を購入している方は、円がドルよりも弱いため、割高な価格で海外の金融商品を購入することになってしまいます。 - 輸入品の値段が上がる
日本の食料自給率は比較的低く、多くのものを海外から輸入しています。
例えば外国産の肉、魚、チーズ、小麦、オリーブオイルなど、生活に密接した食品が値上がりします。
それだけでなく、日本は石油などのエネルギーも輸入しているため、ガソリン価格だけでなく輸送費も上がり、あらゆる物品の価格上昇につながります。 - 海外旅行にかかる費用が高くなる
円が弱いため、海外旅行をするにはより多くの円が必要になります。
つまり、航空券の料金やホテル代、現地での観光費用などが割高になります。 - 日本の輸入企業や内需向け企業にとって厳しい状況になる
海外から物を輸入したり、主に国内向けに事業を展開する内需企業は、円安下ではコストが上がり、利益が減少しやすくなります。
そのため、国内向けに物やサービスを販売する企業に勤めている方は給料が増えにくく、これらの企業の株を保有している場合も、株価が上がりにくく、配当金も増えにくい傾向があります。

まとめると。。。
すでに米国株を中心に資産を築いている人にとって、円安は“ハッピー”な状況です。
なぜなら、円建てで見た資産価値が増えるからです。
一方で、これから資産を築こうとしている人や、まだ資産が少ない人にとっては、円安は“アンハッピー”な状況とも言えます。
米国株などの購入価格が割高になるうえ、物価全般も上昇しやすいため、生活コストが高くなる傾向があるからです。
円高のメリット・デメリット
次に円高のメリットとデメリットを簡単に紹介します。
円高のメリット
- 米国株など海外の金融商品の円建ての価格が割安になる
FIREを目指したり、将来の資産を増やす目的でS&P500のインデックスファンドなど米国株の金融商品を買い増している方にとっては、円がドルよりも強いため、割安な価格で海外の金融商品を購入することができます。 - 輸入品の値段が下がる
海外から輸入している食品や製品などが安くなります。
また、ガソリン価格も下がりやすくなるため、輸送費が抑えられ、さまざまな物品の価格も安くなる傾向があります。 - 海外旅行にかかる費用が安くなる
円高時には、航空券の料金やホテル代、現地での観光費用などが割安になります。 - 日本の輸入企業が儲かる
円高時には、海外から相対的に安く物を仕入れることができるため、輸入した商品を国内で販売する企業などは利益を得やすくなります。
また、海外に生産拠点を持つ企業や商社なども、一般的に円高時に有利です。
このような企業に勤めている方は、給料が増える可能性がありますし、日本の輸入関連企業の株を保有している場合は、株価が上がったり配当金が増えたりする可能性があります。
円高のデメリット
- 米国株など海外の金融商品の円建ての評価額が下がる
もしあなたがS&P500のインデックスファンドなど、米国株の金融商品をすでに保有している場合、円高時では円に換算するとより少ない金額に目減りします。
例えば、100ドル分の米国株を保有していたとして、1ドル=100円のときは10,000円の価値ですが、1ドル=50円に円高が進むと、5,000円と日本円で価値が半分になります。 - 日本の輸出企業にとって厳しい状況になる
海外に物やサービスを販売している企業にとっては、円建てで換算した売上が目減りするため、利益が減少しやすくなります。
そのため、輸出企業に勤めている方は給料が増えにくく、これらの企業の株を保有している場合も、株価が上がりにくく、配当金も増えにくい傾向があります。



まとめると。。。
これから米国株を中心に投資をして資産を増やそうとしている人にとっては、円高は“ハッピー”な状況です。
なぜなら、円が強いおかげで、より少ない円で海外の株を購入できるからです。
また、海外からの輸入品も安くなるため、生活コストを抑えられる可能性が高く、資産形成に追い風と言えるでしょう。
一方で、すでに米国株を中心に資産を築いている人にとっては、円高は“アンハッピー”な状況と言えます。
なぜなら、円換算で見た資産価値が減少してしまうからです。
為替リスクを考慮した私の投資方針
円高・円安それぞれのメリットとデメリットを踏まえ、私は次のような投資方針を取っています。
投資対象
私は早期にFIREを達成するため、米国のS&P500指数に連動するインデックスファンドをメインに投資しています。
過去のチャートを振り返ると、日経平均株価よりもS&P500のほうが明らかに毎年の伸び率が高く、歴史的に見ても米国株のほうが日本株よりも成長する可能性が高いと考えるためです。
ただし、FIRE達成後、円高が進行して資産が目減りするリスクに備える必要があります。
そこで、円高局面に強い日本株、具体的には小売り、食品、IT、商社の株などもポートフォリオに組み込んでいます。
もっとも、日本株の比率を高めることでリスクヘッジにはなりますが、その分、資産の成長スピードは鈍化すると考えています。
したがって、ポートフォリオ全体の8割以上は、S&P500インデックスファンドをはじめとする米国株で構成するようにしています。
いつ、どれだけ買うか
基本的には、毎月一定の金額で金融商品を購入するドルコスト平均法を実践しています。
これにより、円高などで株価が安いときにはより多く、円安などで株価が高いときにはより少なく金融商品に投資することができます。
ただ、常にもしもの時に備えて、約1年分の生活費に相当する現金を銀行口座に残しておき、不況や有事で株価が暴落したり、円高が進行して米国株が割安になったときに、一気に買い増しができるようにしています。
これにより、円高の局面でも攻めの投資を行うことができます。
実際、私はコロナ禍で株安が進んだ際に株を買い増し、その後大きく資産を成長させることができた経験があります。
私自身の為替を意識した行動方針
どこまでいっても将来の相場がどうなるかは誰にも予測できないため、投資だけで為替リスクに対応するのは正直心もとないです。
例えば、円高リスクに備えて日本株を買っていても、将来的に日本経済そのものがダメダメになって、日本株が大きく下落している可能性もゼロではありません。
そのため、投資だけでなく、その他の方法でも為替変動を含むさまざまなリスクに対応できるよう心がけています。
生活コストを上げない
将来、円高や不況で資産が減少した場合でも、生活コストを低く抑えておけば、生活が破綻するリスクを軽減できます。
具体的には、必要十分な広さの部屋に住んで家賃を抑える、車を所有しない、普段は自炊をする、といったことを実践しています。
また、「人は一度生活レベルを上げるとなかなか下げられない」とよく聞くため、昇給や副業などで手取りが増えても、生活レベルを上げないよう心がけています。


稼ぐ力を養っておく
自分自身に稼ぐ力があれば、円高や不況で資産が減少したり、円安で外国株への購買力が下がった場合でも、その悪影響を乗り切りやすくなります。
私の場合、企業に勤めて収入を得る本業のほかに、副業でも収入を得るようにしています。
日本の企業では多くの場合、年功序列の給与体系がまだ根強く残っているため、若いうちに収入を増やすには、企業からの昇給を期待するよりも、副業で収入を得るほうが早いと考えています。
また、FIREを実現した後も、自分自身で稼ぐ力を活かして、自分の好きな働き方で収入を得ることも可能でしょう。
まとめ
為替リスクへの対策としては、私は安いときに多く投資できるドルコスト平均法を活用したり、日本株をポートフォリオに組み込んだりしています。
また、投資だけに頼るのではなく、生活コストを上げないようにすることや、副業によって収入を増やす力を養うことも、早期のFIRE達成、安定したFIRE後の生活のため有効な対策といえるでしょう。

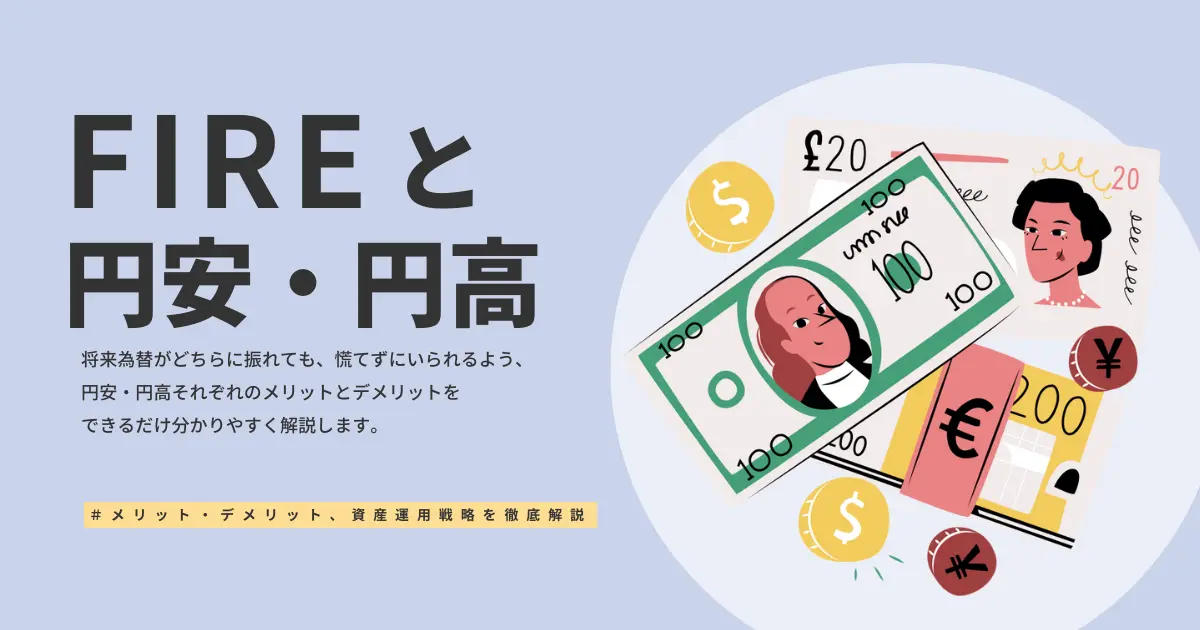
コメント