FIREを最短距離で達成するためには、こちらの3点を実施することが基本となります。
- 収入の最大化
- 投資の活用
- 倹約・節約を通じて生活コストを抑える
しかし、このやり方でFIREを目指す人に共通する大きな課題があります。
それは、「若いときに我慢して節約ばかりして、本当に人生は楽しいのか?」という疑問です。
毎日の節約生活は、ときに辛く感じることもあるかもしれません。
筆者自身も、年に数回の海外旅行など趣味には大きくお金を使うものの、日常生活ではほとんど出費せず、贅沢もしませんでした。
そのため、「今の生き方が本当に正しいのか」と納得しきれずにいました。
そんなときに出会ったのが『DIE WITH ZERO』です。
この本を読んで、「資産をどう最速で増やすか」だけでなく、「いつ、何に使うべきか」を考えるきっかけになりました。
FIREを目指す人の多くは、資産を増やす方法については熱心に取り組んでいる一方で、その資産をどう使うかについては明確な方針や意思を持てていないのではないでしょうか。
今回は、FIREを目指す立場から本書を読んで得られた気づきをまとめます。
『DIE WITH ZERO』とは
『DIE WITH ZERO(直訳:ゼロで死ね)』は、アメリカのコンサルティング会社のCEOであるビル・パーキンス氏が著した「お金の使い方」と「人生観」に関する書籍です。
米国のみならず日本でも大きな反響を呼び、日本国内では累計50万部を突破しています。
センセーショナルなタイトルに加え、近年のFIREブームに一石を投じる内容であることから、多くの注目を集めているといえるでしょう。
FIREを目指す人が『DIE WITH ZERO』から学べること

経験こそが資産
本書は「人生のテーマは、生涯でどれだけポジティブな経験を積めるか」だと強調しています。
体力が落ちた老後にできるのは、これまでの思い出を振り返ることがメイン。
だからこそ、若く元気なうちにどれだけ良い思い出を作れるかが重要だと説いています。
また経験は、自分で振り返るだけでなく、人と共有したり、アドバイスとして語ったりすることで長期的に効力を持ちます。
経験の価値は「複利で高まる」とまで表現されており、この視点は非常に新鮮でした。
モノを買うのに必要なのはライフエネルギー
本書では「モノを買うのに必要なのはお金ではなく、ライフエネルギー(≒時間)」だと説明しています。
ライフエネルギーとは、そのモノを得るために必要なあらゆるコストの合計です。
単純な時給換算だけでなく、通勤時間、仕事に必要なスーツ代、上司や同僚との交際費なども含まれます。
ざっくりでも自分の1時間あたりのライフエネルギーを計算しておくと、「1万円の寿司を食べるにはXX時間分のライフエネルギーが必要」と具体的に考えられるようになります。
本書のメッセージは明確です。
ライフエネルギーを「お金を稼ぐ仕事の時間」と「人生を豊かにする経験の時間」に最適に振り分けることが、最高の人生につながるということ。
もし人生の大部分を仕事に費やしてしまえば、リタイア後に時間と資産が十分にあっても有効にお金を使えず、結局死ぬまでに資産をゼロにできない。
つまり「無駄にライフエネルギーを仕事に費やした」という結末になるのです。
理想は、やりたいこと・挑戦したいことのために必要なお金を稼ぐ分だけ仕事をし、残りの時間はすべて自分や自分の大事な人のために使うことだと説いています。
例えば、一定の資産(1億円など)を築き、元本に手を付けず利回りだけで生きていくFIREのスタイルは、本書の主張からすると「1億円分無駄に働いた。本当はできた1億円分の思い出作りができなかった」という解釈になります。
FIREを目指す自分としても、この指摘にはハッとさせられました。
経済的自由を獲得するために資産を築いていく過程で、逃しているチャンスや経験はないのか?
元本を減らさずにリタイア後を過ごすのは、本当に正しいことなのか?
むしろ「リタイア後に徐々に資産を取り崩すこと」を前提に目標額を設定すべきなのではないか?
――そんな疑問が自分の中で湧いてきて、改めて自分のFIREのあり方を見直すきっかけになりました。
人生の自動運転モードをやめる
スタバでコーヒーを買う、ペットボトル飲料を買う、コンビニでお菓子を買う——こうした毎日の行動は本当に自分に満足をもたらしているのか分からないまま、なんとなく続けている習慣かもしれません。
本書では、これを「自動運転モード」と呼んでいます。
著者は、こうした小さな日々の出費に対しても「自分の限られたライフエネルギー(≒時間)を本当に使うべきか」を意識して考えるべきだと提唱しています。
これはダイエットの例に似ています。クッキーを1枚食べたら、そのカロリーを消費するためにどれだけ運動が必要かを考えるのと同じ感覚です。
また、自動運転モードをやめるべきなのはお金の使い方だけではありません。
お金を稼ぐ、つまり働くことについても同じです。
十分な資産があるのに「まだ定年じゃないから、同年代の皆が働いているから」という理由だけで仕事を続けるのはやめるべきだ、と本書は指摘します。
大切なのは、自分は日々年を重ねており、与えられた時間は有限だという事実を意識し、毎日の行動を自分の意思で選ぶことだと説かれています。
支出を収入カーブに合わせない
新卒で会社に入ったばかりの頃、給料が安い若手社員のうちは節約し、「欲しいものややりたいことは、昇進して稼げるようになってから、ある程度の貯金ができてから」と考えたことはありませんか?
本書はこの考え方をはっきりと否定しています。
なぜなら、若くて時間や体力があるときに使えるお金と、老後に使えるお金の価値はまったく違うからです。
例えば「マチュピチュに行きたい」という夢があったとしましょう。
若い頃に「給料がまだ安いから、貯金がないから」と先送りにしたとしても、いざ十分な収入を得たときには――
体力が落ちて長時間フライトや高地での観光がきつくなっている
役職がつき、気軽に長期休暇が取れなくなっている
子どもが生まれて自由に動きにくくなっている
このように、様々な障害が出てくる可能性があります。
だからこそ本書は、「やりたいこと、挑戦したいことがあるなら“今すぐやれ”」と強く訴えています。
お金については「将来自分の給料が上がるから大丈夫」という考えで、未来の自分から前借するイメージです。
また、本書はデータをもとに「年齢を重ねるごとに、医療費を考慮しても年間支出は減っていく」と主張しています。
アメリカの事例なので日本と完全には一致しませんが、日本は公的保険が充実して医療費も比較的低く抑えられるため、同じく高齢になるほど「体力や健康の制約でお金を使えなくなる」という傾向は当てはまりそうです。
つまり――「どうせ年をとったら時間や健康面での制約が出てきて使えるお金が減っていくのだから、年を取ってからではできない経験に、若いうちからお金を使うべきだ」という主張には大きな納得感がありました。
FIREを意識すると、「今は我慢、将来の自由のために貯める」という思考に偏りがちです。
しかし、それは「若いときにしかできない経験」を犠牲にするリスクを孕んでいることを本書では警告しています。
DIE WITH ZEROを受けて私はどうするか
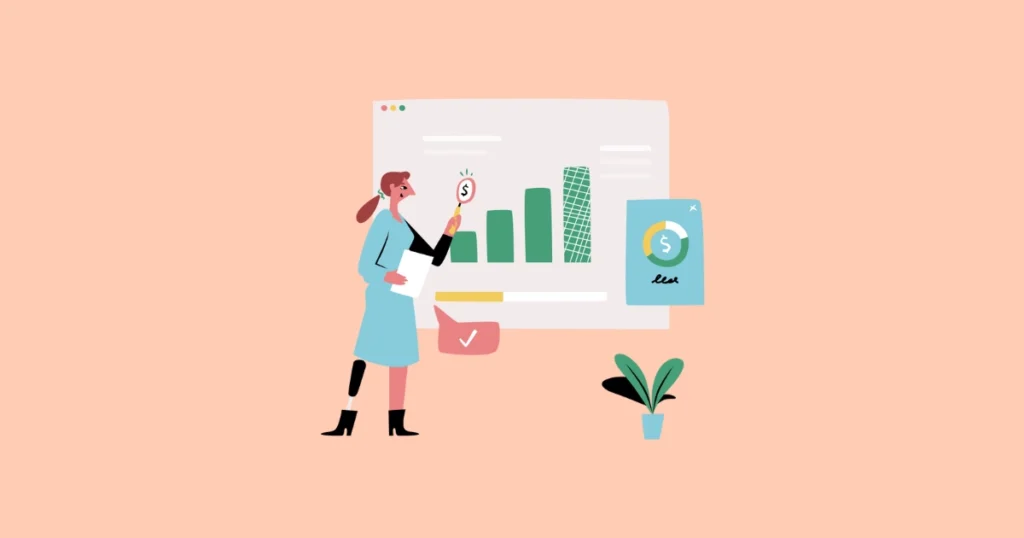
資産を取り崩すタイミングを検討してみる
本書では「死ぬまでに必要な最低限のお金」は、
毎年の生活費 × 残りの寿命年数 × 70%
で大まかに算出できると説かれています。
この70%という数字は、資産が年利3%で成長することを前提にしており、決して楽観的な見積もりではありません。
また「資産を取り崩して、老後にお金が尽きてしまうのではないか」という不安を抱える人には、平均寿命ではなく人類の最長寿命を基準に計算すれば安心できる、としています。
私の場合、夫婦2人の年間生活費は180万円です。
この条件で試算すると、資産が約1億円に達した時点で「資産を減らし始めてもよい段階」に入ることが分かりました。
私たち夫婦が掲げているFIRE達成のための目標額は1億886万8,000円です。
したがって、完全FIREを目指すにせよ、元本を切り崩すにせよ、当面は「1億円」が一つの基準になると改めて明確になりました。
『DIE WITH ZERO』の考え方に従えば、年齢を重ねるほど必要な資産額は減っていきます。
また、物価変動によって生活費自体も変動します。
そのため、数年に一度は計算を見直すことが重要だと感じました。
年齢別やりたいことリストを作る
加齢による体力の衰えなどを考えると、やりたいことを実行できる最適な時期はある程度限られてきます(たとえば激しいスポーツは30代までなど)。
そこで本書では、費用のことはいったん脇に置き、「やってみたいこと」「チャレンジしたいこと」をリストアップし、5年刻み、もしくは10年刻みの年齢軸にプロットすることを推奨しています。
これにより、やりたいことを単に列挙するだけでなく、「何歳までにやるべきか」が可視化されます。
私自身もこのリストを作ってみて、「大してお金もかからず、ハードルも低いのに、まだ実現できていないことが意外に多い」と気づきました。
例えば、以前から漠然と「キャンプをしてみたい」と思っていたものの、このリストを作るまでずっとできずにいました。
海外旅行などよりもハードルは低く、「いつでもできる」という感覚から、無意識のうちに先送りにしていたのでしょう。
しかし、キャンプなら週末にでもすぐ実行できます。
実際にリスト化したことで、キャンプグッズを集め始めるといった行動の変化が生まれました。
FIREを目指して資産形成に励む中でも、後悔しないように、「今の年齢だからこそ最大限楽しめる経験」にお金を使うことは、FIREを志す人にとっても合理的なお金の使い方ではないでしょうか。
死ぬまでに残された時間を意識する
本書では、「LIFE LEFT」など残りの寿命を可視化できるアプリをダウンロードすることを推奨しています。
余命を意識することは確かに怖いですが、残された時間を意識することで先送り癖を抑え、「今できることをすぐやる」という行動力につながります。
また、時間の貴重さを理解したうえで、時短家電や家事代行を積極的に活用することも推奨されています。
私自身、食洗機を使っていて家事の負担が大幅に軽減された経験があるため、少なくとも食洗機は強くおすすめできる時短家電です。
浮いた時間を家族との団らん、副業、休息などに充てることができます。
家事代行についてはこれまで利用したことはありませんが、特にコンロ掃除のように労力のかかる家事は、依頼してみるのも一つの選択肢だと感じました。
健康に投資する
本書では、「老後の医療費を恐れるより、今から健康に投資して予防すること」を勧めています。
これは単に将来の医療費を抑えるだけでなく、健康寿命を延ばし、より多くの経験を積める時間を増やすことにもつながります。
私自身、食事には気を使っており、旅行中以外はお酒を飲まず、普段は自炊中心で玄米を取り入れるなど工夫しています。
一方で運動は、通勤で歩く程度で、筋トレはサボりがちです。
今後はスクワットなどの筋トレを習慣的に続けていきたいと思いました。

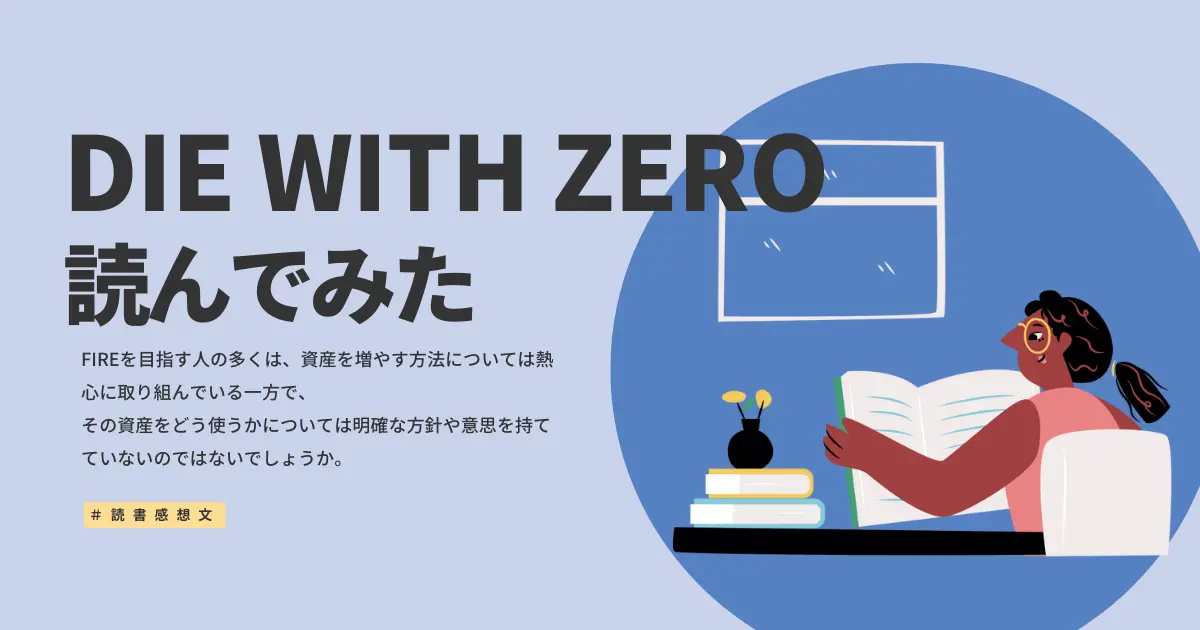
コメント